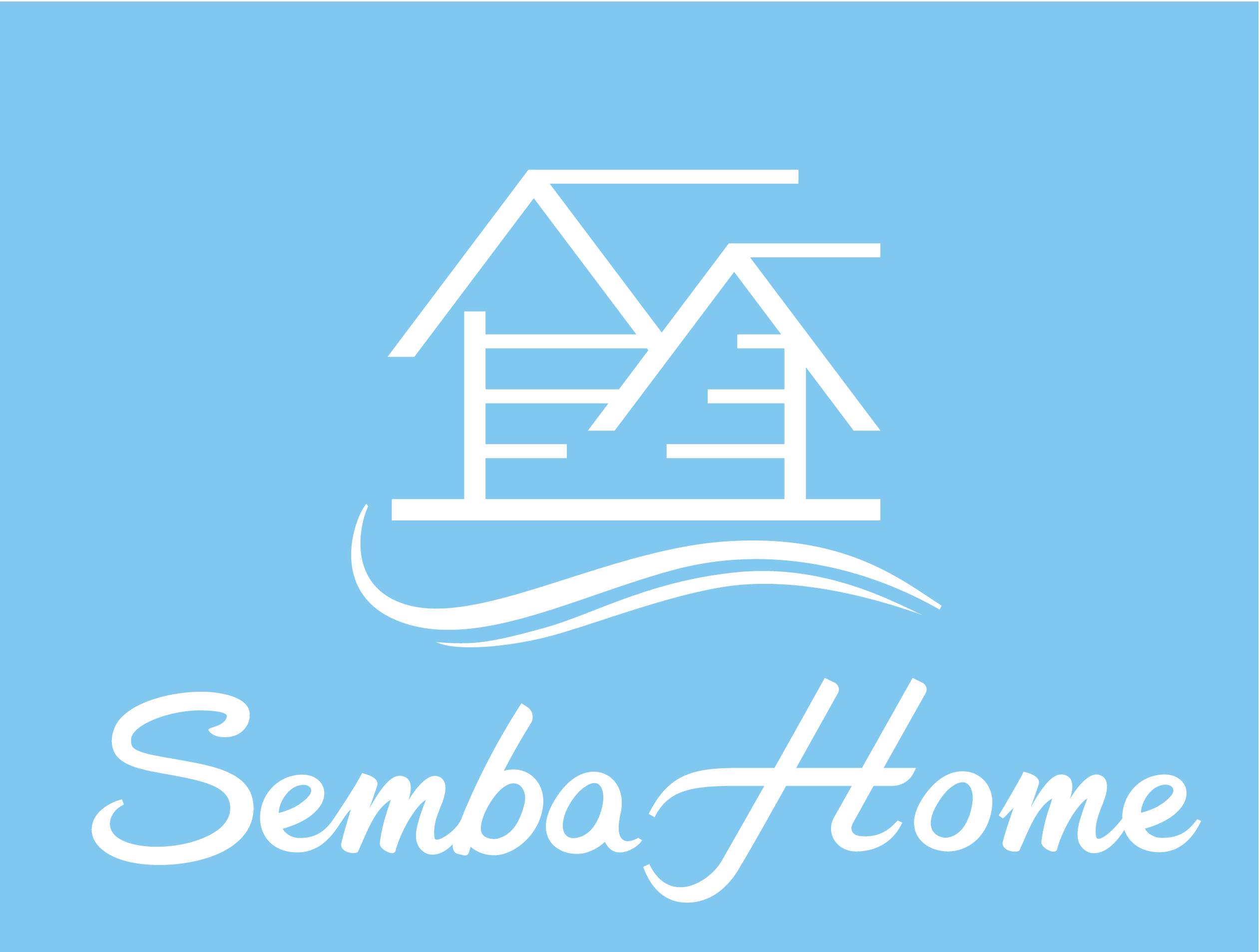死のガイドラインって聞いたことある?
事故物件の告知義務をやさしく解説

「死のガイドライン」とは、国土交通省が2021年10月8日に正式発表した 「宅地建物取引業者による人の死の告知に関するガイドライン」の通称です。この指針は、事故物件と呼ばれる“人が亡くなった物件”に関して、不動産業者がどのように告知すべきかを明確にし、公正で安心な取引を促す目的で策定されました。
事故物件の定義が曖昧だった従来では、業者によって対応がバラバラで、トラブルや流通の停滞を招いていました。その課題を受けて、国交省は、実務や裁判例を踏まえた統一基準の提供に踏み切ったのです。
「告知」の必要・不要のルールって?

告知が不要なケース
ガイドラインでは、以下のようなケースは、原則として「告知しなくてよい」とされています:
自然死や誤嚥、転倒など、日常生活の中での不慮の死亡:告知不要とされます。
賃貸物件で、発生から概ね3年が経過した死(特殊清掃を含む):告知義務は消滅するとされています。
隣の部屋や共用部分(通常使わない範囲)での死亡:原則、告知不要。ただし周知性や事件性が高い場合は例外となります。
告知が必要なケース
一方で、次のような場合には、たとえ時間が経過していても告知が必要です:
事件性の高い内容(自殺・殺人・事故死など)や、ニュース等で広く知られた事案。
- 買主・借主から問い合わせがあった場合:「心理的瑕疵」に該当するとみなされ、事実を伝える義務があります。
特殊清掃など発覚やリフォームを伴うケース:これらの事実も告知対象です。
宅建業者の調査義務とは?
「死のガイドライン」が示すもう一つの大きなポイントは、不動産会社(宅建業者)がどこまで調べる義務を負うのか、という調査義務の範囲です。
国土交通省や不動産ポータルサイト「ライフルホームズ」の解説によれば、宅建業者は、媒介契約を結んだ際に売主や貸主に「告知書」や「物件状況報告書」などへの記載を求めることで、通常の調査義務を果たしたとみなされます。
つまり、「まずは当事者からの申告を受け取る」というのが基本スタンスであり、これ以上の積極的な調査──例えば、周辺住民に聞き込みを行う、過去のニュース記事やSNSを検索するといった行為──までを義務として課されるわけではありません。
もっとも、業者が自発的に追加調査を行うケースもあります。例えば、同じ建物内で以前に事件があったと噂されている場合や、契約者から強い不安の声があった場合などです。ただし、こうした調査をする際には遺族や関係者の名誉、プライバシーへの配慮が不可欠です。むやみに近隣住民へ詳細を聞き回ると、思わぬトラブルを招くこともあるため、慎重な対応が求められます。
さらに、告知書に「特に該当なし」と記載されていても、宅建業者側に重大な過失がない限りは、調査義務を果たしたと扱われます。この“重大な過失”とは、例えば過去に報道や裁判記録で明らかになっている事件を知りながら見過ごすようなケースを指します。

告知義務を怠るとどうなる?
もし宅建業者が告知義務を怠った場合、法律的にもビジネス的にも大きなリスクが生じます。
まず考えられるのは、契約解除や損害賠償請求です。売買契約や賃貸契約において、事故物件であることを告げずに契約を結ぶと、「契約不適合責任」や従来の「瑕疵担保責任」に基づき、契約を取り消されたり、損害賠償を請求されたりする可能性があります。これは購入者や入居者が心理的瑕疵を理由に契約を解消する権利を持つためです。
次に、行政監督による評価です。宅建業者は宅地建物取引業法の規制下にあり、行政処分の可能性もゼロではありません。国土交通省のガイドラインはあくまで“法的拘束力を持つ法律”ではありませんが、監督行政の現場では判断の参考基準として活用されます。そのため、ガイドラインに沿わない対応をすると、「対応の妥当性が欠けている」と指摘される恐れがあります。
こうしたリスクを避けるためには、告知の必要がある場合は必ず誠実に説明し、記録に残すことが重要です。
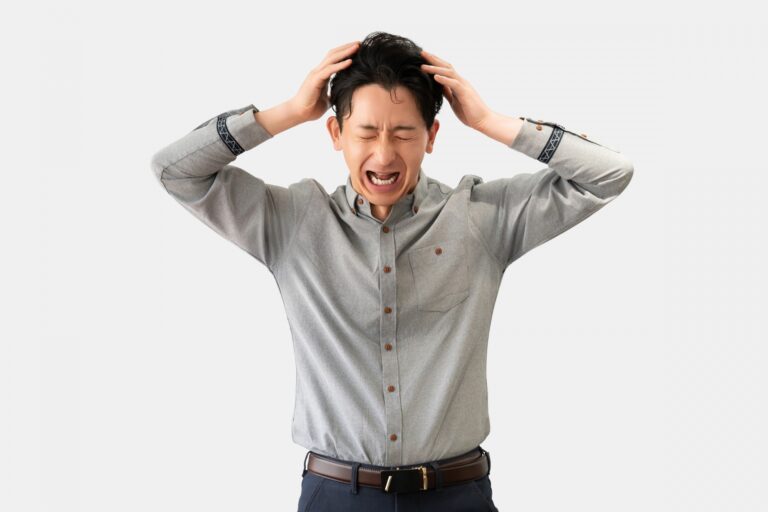
不動産を探す側が知っておくべきこと
「死のガイドライン」は、宅建業者向けの指針ですが、実は物件を探す側にとっても知っておくと役立つ情報がたくさん含まれています。
最も大切なのは、遠慮せずに質問することです。たとえば、「この物件で過去に人の死はありましたか?」と単刀直入に聞いて構いません。もし告知義務がある内容であれば、不動産会社は正直に回答する必要があります。
また、内見や契約前の段階で「告知書」や「履歴調査」の確認をお願いするのも有効です。履歴調査とは、過去の取引履歴や登記情報、リフォーム記録などを確認する作業で、心理的瑕疵の有無を推測する材料になります。
さらに、内見時には物件内部だけでなく、周辺環境や共用部分もチェックしましょう。事故物件であった場合、共用部分や外観に手を加えた形跡が残っていることもあります。こうした小さなサインを見逃さないようにすることで、より安心した選択が可能になります。
重要なのは、「何となく聞きづらい…」と感じて曖昧にしないことです。質問した記録を残し、答えも文面で受け取っておくと、後々のトラブル予防にもなります。

まとめ
「死のガイドライン」は、不動産取引における「人の死」に関する告知ルールを体系的に整理し、取引の透明性と安全性を高める画期的な指針です。
この指針によって、自然死や経過年数による告知不要のケースが明文化される一方、事件性のある死亡や問い合わせがあった場合には必ず告知することが求められます。また、宅建業者の調査義務の範囲も明確になり、売主・買主・借主・業者すべてが同じ基準で判断できる環境が整いました。
不動産会社にとっては、トラブル防止と信頼確保のための実務指針として活用でき、物件を探す側にとっては、安心して取引するための質問ポイントが見える化されたと言えます。
結局のところ、このガイドラインの本質は「知っていれば防げるトラブルをなくすこと」です。買う側も売る側も、そして仲介する業者も、このルールを正しく理解し、取引の場で活かしていくことが、安心できる不動産市場をつくる第一歩となります。
そして、こうした複雑な告知義務や調査の判断に迷ったときは、私たち船場ホームにご相談ください。経験豊富なスタッフが、法律やガイドラインに沿った適切な対応と、安心できるお部屋探し・売却のサポートを全力でいたします。安心と信頼の不動産取引は、船場ホームから。

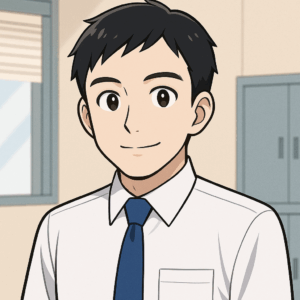
この記事を書いた人
奥田 貫太(おくだ かんた)|船場ホーム 代表
宅建業界に携わって10年以上。現在は船場ホームの代表として、住まい選びと住宅ローンのご相談を中心に、お客様の暮らしに寄り添うサポートを行っています。
とくに住宅ローンの仕組みや金利の選び方には詳しく、将来を見据えた無理のない資金計画づくりを得意としています。
趣味はサッカーと映画鑑賞。「住宅ローン、なんとなく選んでいいのかな…?」そんな不安があれば、どうぞお気軽にご相談ください。